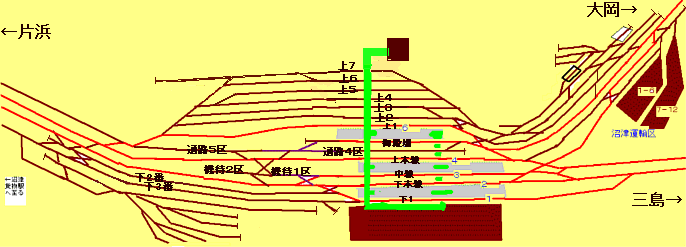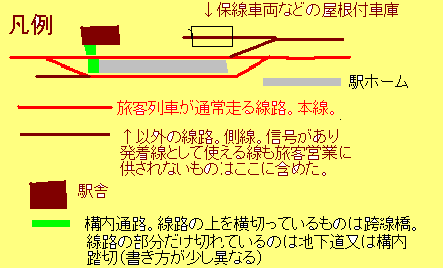
静岡県内鉄道各路線の前面展望/配線図
前面展望:東海道線 熱海−函南 函南−沼津 沼津−原 原−冨士 冨士−蒲原 蒲原−清水 清水−静岡
静岡−焼津 焼津−金谷 金谷−掛川 掛川−磐田 磐田−浜松
浜松−舞阪 舞阪−鷲津 鷲津−豊橋
前面展望:御殿場線 国府津〜松田 松田〜谷峨 谷峨〜足柄 足柄〜御殿場
御殿場〜富士岡 富士岡〜裾野 裾野〜沼津
前面展望:伊東線 伊豆急行 伊豆箱根鉄道駿豆線 大雄山線 天竜浜名湖鉄道(後方展望)
※静岡県内私鉄路線の前面展望につきましては「たわたわのページ」(川柳五七さん運営)で
紹介されています。ぜひそちらもご覧ください。
「たわたわのページ」内前面展望画像の紹介ページへ→
伊東線・伊豆急行 伊豆箱根鉄道駿豆線 岳南鉄道 静岡鉄道 大井川鐵道
配線図 御殿場線配線図 東海道線(熱海ー静岡)配線図 東海道線(静岡−豊橋)配線図
身延線(冨士−身延)配線図 身延線(塩之沢−甲府)配線図 伊東線配線図
伊豆急行配線図 伊豆箱根鉄道駿豆線 岳南鉄道配線図 静岡鉄道配線図
大井川鐵道(大井川本線)配線図 遠州鉄道配線図 天竜浜名湖鉄道配線図
※当ホームページはフレーム構造を採用しております。フレームが表示されない場合はホームページトップより入り直して下さい。
※当コーナーは可能の限り私の記憶に基づいています。なお、参考資料は次の通りです。
「東海道570駅」小学館・宮脇俊三/原田勝正編集(92.11.10第1版)
「沼津機関区100年史」 国鉄沼津機関区 (昭和61年7月の沼津機関区公開時に購入)
「JTB時刻表99年7月号」JTB (キロ程の数字を利用しました)
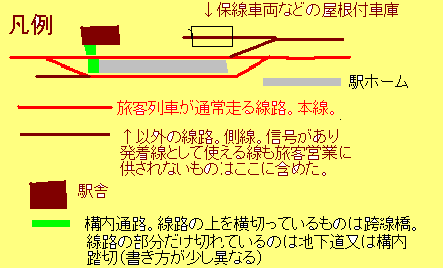
国府津 起点0Km 明治20年7月11日開業
御殿場線の起点である。御殿場線は通常3番線を使用するが、東京直通などで2、4番線を
使用する列車も ある。国府津運転所があり、東海道線の通勤輸送の拠点として重要な駅である。
かつては機関区があったが跡形もない。発車してしばらくは複線のようであるが1本は
国府津車両センターへの出入庫線である。右から貨物線が合流しすぐに新幹線と小田原厚木道路をくぐる。
そこから国府津車両センターの留置線が始まる。広大な車両基地が終わりしばらくすると下曽我である。
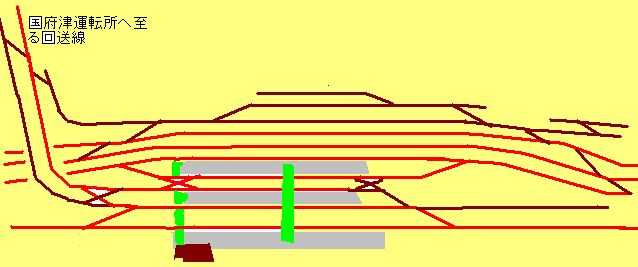
下曽我 起点3.8Km 大正11年5月15日開業
JR東海に入って最初の駅。セメントサイロがあって秩父鉄道の武州原谷駅から
セメント貨車が入線していたが、平成10年10月改正で貨物列車はなくなってしまった。
過去には他にも酒匂川まで専用線が延びていたようだ。
ちなみに上り本線は御殿場方面への折返し運転も可能だ。
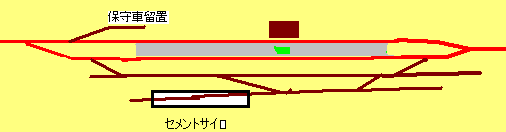
上大井 起点6.5Km 駅間2.7Km 昭和23年6月1日開業
交換がないときは下り列車でも駅舎側のホームに止まる。
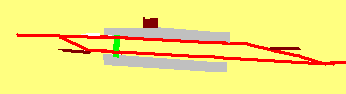
相模金子 起点8.3Km 駅間1.8Km 昭和31年12月25日開業
築堤の上にある片面ホームだけの無人駅。周囲は畑と住宅地が入り混じっている。
![]()
松田 起点10.2Km 駅間1.9Km 明治22年2月1日開業
川音川を渡ったところから駅構内に入る。松田で小田急と接続する。特急あさぎりは1番線から発車する。
乗客の多くは地下道をくぐった小田急側の改札口を利用する。改札前の横断歩道を渡って
すぐ目の前が小田急新松田駅である。駅前にはコンビニ(小田急OX)もある。
松田駅は開業当時からの駅である。開業当時の御殿場線は東海道本線の一部であり、
当時は松田、山北、小山(現、駿河小山)、御殿場、佐野(現、裾野)の駅があった。
駅の海側(沼津に向かって左側)にはかつての貨物側線が2線と積み下ろし設備の痕跡が残っている。
かつては酒匂川まで砂利採取の貨物線が延びていたらしい。出発してすぐ左側の幼稚園の敷地内を
突っ切っていたようだ。 松田を出てしばらくすると左には酒匂川が、右には国道246号と東名高速道路が併走する。
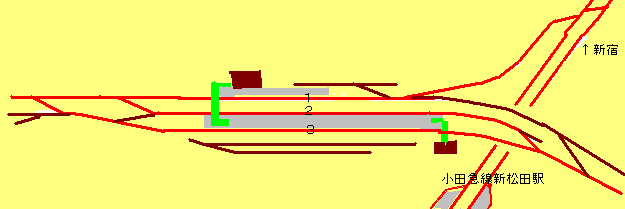
東山北 起点13.1Km 駅間2.9Km 昭和31年12月25日開業
相模金子と同時に開業した、片面ホーム1面のみの無人駅である。
築堤上にある。近くに高校があり高校生の乗降が多い。東山北を出ると
再び国道246号と東名高速道路と併走する。しばらくして左にカーブして246号をくぐり少し行くと山北である。
![]()
山北 起点15.9Km 駅間2.8Km 明治22年2月1日開業
現在でこそ単なる中間駅となってしまったが、かつては御殿場までの
連続25‰勾配(1000m走ると25m標高が高くなる)を登り切るための
補助機関車の基地であった。「沼津機関区100年史」によると、現在のホームと駅舎の間には
現在ある2本を含め6本と、反対側は現在留置線となっている側線が下り本線で機回し線を含め7線、
さらに東側にターンテーブルと扇形庫14線、上り方/下り方に引き上げ線各2線と
かなり大きな駅であったことが分かる。昭和9年12月1日に丹那トンネルが開通すると
1支線になった御殿場線は輸送量が凋落し、昭和18年5月15日に山北機関区は
廃止されてしまった。現在は上下本線に側線が3本のみだが敷地を見ると
「そこにレールが敷かれていたんだなぁ〜」というのがよく分かる。駅の反対側には
かつて御殿場線を走っていたD52 70が保存されている。(その場所もかつての山北機関区の敷地だった)
山北では一部の列車が折り返す。また夜間に東京からの113系4連と313系/211系混結4連が駐泊する。
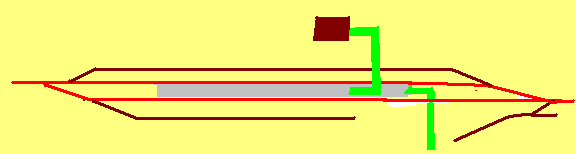
この駅の沼津寄りのところには掘割を走る線路の両側に桜の木が植わっている個所があり、
有名撮影地となっている。またここから駿河小山にかけては蛇行して狭い谷間に
酒匂川・国道246号・御殿場線がひしめいており、トンネルや橋梁が多い。かつて複線だった頃の
名残のトンネル・橋台なども見受けられる。東名高速道路は山北から谷峨にかけては
都夫良野トンネルで抜けている。またこのあたりは東名高速では唯一上下線が離れている。
トンネルを2本くぐり少しして酒匂川を渡る。この部分では国道246号はバイパス化されている。
さらに2回橋を渡りトンネルをくぐる。このトンネル、かつては2本のトンネルだったが
関東大震災の際の土砂崩壊で埋まり、復旧工事の際に1本に繋いだものである。
この部分は前後とでトンネル構造が変わっているので分かりやすい。トンネルを抜けて少しいくと谷峨である。
谷峨 起点20.0Km 駅間4.1Km 昭和22年7月15日開業
駅としては新しいが、信号所としては大正9年2月12日に設置された。
辺りは谷間で小さな集落がある。丹沢湖方面へのハイキング客/キャンプの
玄関口である。無人駅。駅舎は最近になって建て替えられた。
東名高速道路は駅の北側で都夫良野トンネルを出て、駅の西側で谷を横断する。
桜の時期には山北に次ぐ撮影スポットとなる。朝にはあさぎり同士の交換がある。
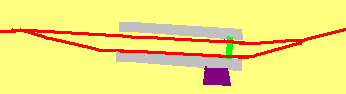
谷峨を出てすぐトンネルをくぐるが、かつての上り線はトンネルをくぐると
川を渡り国道246側を走っていた。もっとも国道246拡張で痕跡はほとんど残っていない。
残っている痕跡というと川を渡る橋脚ぐらいか。何度か川を渡りトンネルをくぐる。
最後のトンネルをくぐる辺りが神奈川/静岡県境である。川の名前も鮎沢川に変わる。
駿河小山 起点24.6Km 駅間4.6Km 明治22年2月1日開業
静岡県に入って最初の駅。近くに紡績工場がありその倉庫との間に専用線があった。
現在その線路は保線車両の留置線になっている。また下り線側にも側線が2本と引き上げ線があった。
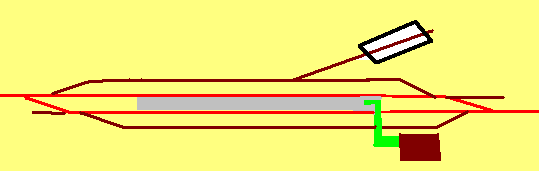
この辺りから谷が少し広くなり、山越しに富士山が見えるようになる。
少し行くと東名高速道路(下り線)と上り線がオーバークロスする。
上り線はさらに下り線を跨いでおり径の大きい斜張橋になっている。
足柄 起点28.9Km 駅間4.3Km 昭和22年9月15日開業
この駅も信号所が格上げされた駅である。近くに小山高校があり高校生の利用があるが
普段はひっそりとした駅である。同じ足柄でも小田急の足柄駅とは全然違うところなので注意。無人駅。
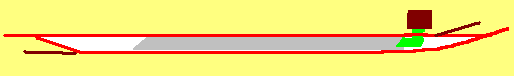
しばらく行くと急に谷が開け、田園地帯になる。そして大きな富士山が!!
ここも有名撮影地ですが駅からかなりの距離がある。
御殿場 起点35.5Km 駅間6.6Km 明治22年2月1日開業
御殿場線沿線最大の都市、御殿場駅の玄関口である。ここから富士山麓や箱根、山中湖/河口湖方面など
各方面へバスが出ていて交通の要衝になっている。駅の東口からは新宿へ向かう小田急高速バスが発着する。
また駅前は商店街となっている。市内には高校が3校あり、高校生の乗降も多い。
ちょうど駅の辺りが線内ではもっとも標高が高く約450Mである。かつては補助機関車の解結をする駅として
重要な駅だった。かつての特急「燕」では走行中解放を行っていた。2面3線あるが2番線は
御殿場折り返しの列車が発着することが多い。東側の側線2線は電車の留置線となっている。
またかつては貨物扱いもあったが昭和57年11月15日改正で廃止となった。かつての貨物側線のうち
北側は跡形もなく撤去され自転車置き場等になってしまった。南側は御殿場工務所がある関係で保線機械がよく止まっている。
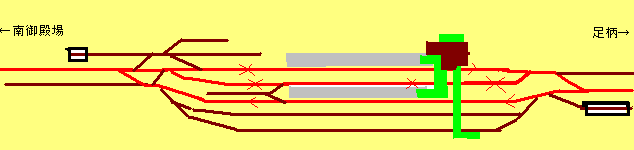
国鉄時代(昭和53年頃)の貨物を取り扱っていた時代の配線図
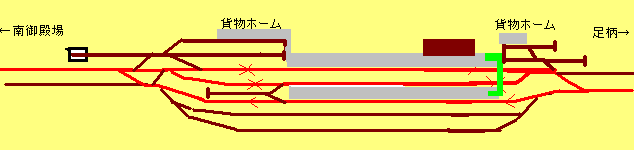
御殿場からは一転下り坂となる。もっとも山北−御殿場のように谷間の険しい地形ではなく
なだらかなゆったりとした地形だ。御殿場市内で見る富士山は雄大だが、下るにつれだんだんと小さくなっていく。
南御殿場 起点38.2Km 駅間2.7Km 昭和37年7月20日開業
片面ホームだけの無人駅。駅前には国道246号の旧道(現在は県道)が走っていて
農協とローソンがある。集落には農家が多い。近年ホームが整備され車椅子用のスロープや点字ブロックが備え付けられ
また送迎車の停車レーンも設置された。春になると北側の桜の木がきれいだ。
![]()
駅の南で県道がアンダークロスして東側に出る。県道沿いに集落が栄えているが線路の西側は田園地帯である。
富士岡 起点40.6Km 駅間2.4Km 昭和19年8月1日開業
昔はスイッチバック式の信号所だった。御殿場−裾野間も25‰の連続勾配が続いているのでスイッチバックで
ないと止められなかったのである。それも昭和43年の電化とともに廃止となり
その後長らく片面ホーム1面だけの駅であった。平成2年に行き違い設備の新設工事が行われ現在の駅となった。
片面ホームは駅舎の北側(図の右側)にあったが現在の島式ホームは南側に新設したものである。
かつてのスイッチバック跡の盛土は行き違い設備工事の際に一部崩されたもののほとんどの部分はそのまま残っている。
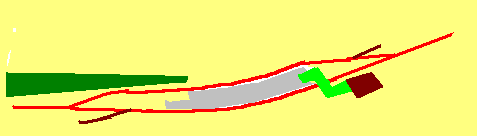
富士岡−岩波間は途中から森の中の堀割を進む。森が切れた辺りで右側に大きな工場が見える。
トヨタ自動車の組み立て下請けの関東自動車工業の工場で、かつてはこの辺りで
専用線が分かれていてク5000によって自動車輸送が行われていた。
昭和57年11月15日改正で廃止になったがその廃線跡は今でも残っている。
一部の敷地は東名高速道路裾野インター建設に転用された。
岩波 起点45.3Km 駅間4.7Km 昭和19年12月8日開業
この駅も富士岡駅と同じく、信号所→駅、スイッチバック→棒線駅→交換駅という経歴を歩んできた。
行き違い設備の建設は、従来あった片面ホームの反対側を削って島式化した。
ただ、裾野方の分岐機は地形の関係で両開きとなり45Km/h制限となっている。
保線機械留置線が1線ある。この駅から裾野市である。工場への利用者が多い。
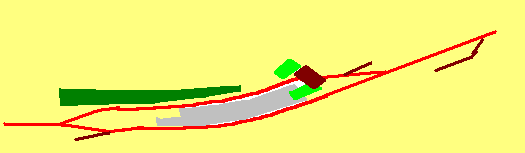
国鉄時代(昭和53年頃)の貨物を取り扱っていた時代の配線図
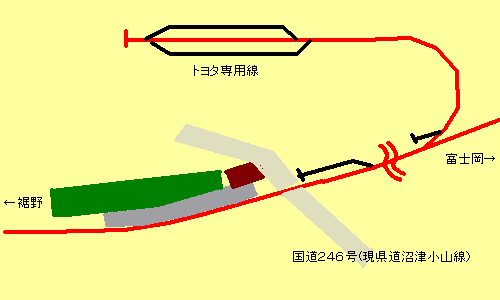
現在の上り方の安全側線付近に保線用側線が設けられていた。
トヨタ専用線は側線3本の割と単純な引込み線だったようだ。
なお専用線との合流手前にはそれぞれ信号機が設置されていた。
昭和53年頃の貨物列車の大雑把な時刻は以下の通り
岩波行き DE11+ク5000×8車+車掌車(たまに車カバー返却のためのワムが1両ついてきた)
裾野駅基準9:46頃通過 返しは14:20頃
御殿場行き EF60+ヨ+黒ワム+ヨなど 車掌車は2両ついたがワムは2両とか短いことが多かった。
ただ、時折チキが6両ぐらい戦車積載で繋がって来ることもあった。
裾野駅基準10:10頃発(裾野駅で下り列車と交換) 返しは19:0頃
下土狩行き DE11+ワム数車+タキ又はホキ だと思うのだが見たことがないに等しかったり・・・。
沼津発が9時台前半ぐらいだと思うのですが・・・。
裾野 起点50.7Km 駅間5.4Km 明治22年2月1日開業
裾野市の中心駅。高校が1校あり利用者が多い。かつては沼津方より裾野折り返しの列車が運転されていた。
現在でも折り返し用の信号機があり列車の設定は可能である。かなり前には貨物の取り扱いもあった。
ここから御殿場までは25‰勾配になっており、駅構内にある踏切から御殿場方向を見るといかに坂が急かが分かる。
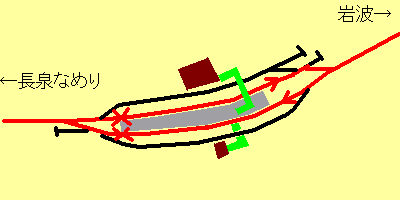
国鉄時代(昭和53年頃)の配線図(既に貨物は廃止済み)
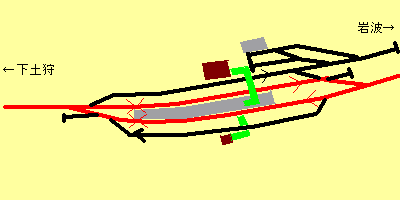
現在は保線用側線となっている上下本線両側の側線だが信号機が設置されていた。
また下り線側も架線があった。現在の西口自転車置き場はかつての貨物側線の跡地。
長泉なめり 起点53.5km 駅間2.8Km 平成14年9月7日開業
御殿場線でもっとも新しく平成14年に開業した駅。駅西側3Kmのところにある静岡ガンセンターへの
最寄駅で整備された駅前からバスが発着する。現在は棒線駅であるが将来交換設備を設置する余地を
残している様だ。東西連絡用の跨線橋が設置され、エレベーター付きとなっている。無人駅。
![]()
下土狩 起点55.6Km 駅間2.1Km 明治31年6月15日開業
かつては三島駅であった。駿豆鉄道(現在の伊豆箱根鉄道線)がここまで延びてきていた。
丹那トンネル開通で駿豆鉄道は現在の三島駅に繋がるようになりこの駅の名も下土狩になった。
貨物の取り扱いを行ってきたが昭和57年11月15日で廃止され貨物を出荷していた精麦工場そのものも
なくなってしまった。跡地の一部は整地され長泉町の文化センターや宅地に変わっている。
現在、この駅も夜間は無人化されてしまった。
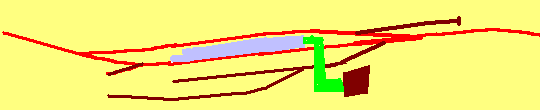
国鉄時代(昭和53年頃)の貨物を取り扱っていた時代の配線図

現在残っているのは上下本線以外は当時の下1番、下2番と引上げ線部分(安全側線として使用)のみである。
よくよく見ると上り線側にも側線の痕跡があるのが見て取れるが私の記憶の時点では既に撤去されていた。
大岡 起点57.8Km 駅間2.2Km 昭和21年1月15日開業
周りは住宅地。工場や高校もある。すぐそばに国道414号線(旧国道246号)が走っている。
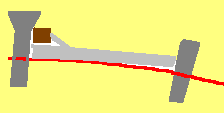
沼津 起点60.2Km 駅間2.4Km 明治21年2月1日開業
静岡県東部の核をなす沼津市の代表駅である。駅前は商店街やデパートが建ち並んでいる。
また各方面へバス(富士急行・伊豆箱根鉄道・東海箱根登山バス)が走っていて交通の要所である。
かつては機関区があり東海道線・御殿場線の機関車、御殿場線・身延線の電車を受け持ってきたが
昭和61年11月に車両配置がなくなった。もっとも現在でも沼津運輸区があり重要な運転拠点であることには
変わりない。かつての機関区跡地には「キラメッセ」というイベントの催事場が建てられた。
駅の片浜方には貨物駅がある。また明電舎がありたまに大物車が出入りしている。
かつては構内を見渡せば多種多彩な貨車が見られたものだがコキ車のみとなり寂しくなったものだ。
御殿場線は主に5番線を使用しているが、浜松行きなど東海道線下り方面直通/あさぎりは2/3番線へ、
5番線が埋まっているときには6番線を使用できる。反対に御殿場線に入る列車は3,5,6番線から発車することができる。
東海道線は1,2番線が下り、3,4,6番線は上り列車が使用する。3番線は沼津折り返し列車(東京直通が多い)の
使用が多いが、下り方面にも出ることができる。